2022年10月25日
八十二銀行の「耳マーク」
《過去ログピックアップ》

於 八十二銀行 塩尻支店(大門一番町11−10)
別コーナーの金融相談にも、
もちろん、筆談で応じるという。
身体障がい者手帳のあるなしには関係ない。
耳が不自由であることを口頭で伝えるだけでよい。
(元記事 2016.6.22)
於 八十二銀行 塩尻支店(大門一番町11−10)
別コーナーの金融相談にも、
もちろん、筆談で応じるという。
身体障がい者手帳のあるなしには関係ない。
耳が不自由であることを口頭で伝えるだけでよい。
(元記事 2016.6.22)
2017年02月16日
筆談マークについて
筆談マークについて
筆談マークについてコリさんのコメントから
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニシダさんの掲示板2/10より
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生臭坊主
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
みみばあちゃん
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニシダ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生臭坊主
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ROKU
貴重な書き込みをたくさんいただきました。
ありがとうございました。


これは、災害避難所用のビブスです。塩尻では2種類作りました。
聾者は、たいがい、「聞こえません」の方を選択しし、
難聴者は、たいがい、「耳が不自由です」の方を選択しています。
当初は「聞こえません」一本であったのですが。
難聴者側から、「表現が常識外れだ」という意見が出て、
「耳が不自由です」が加えられた。
ところが、聾者は、
「耳が不自由」という表現は、ピンとこない」
「聞こえるのか聞こえないのか、はっきり表現しないとわからない」
と仰る。その結果二本立てとなった。
聾者のみなさんは、婉曲的な、あるいは抽象的な表現は苦手のようです。
それがいけない、というのではなく、
それが「ろう文化」であると私は理解しております。
そういう意味で、「耳マーク」は、聾者にとって、、なにか不思議なマークにしか見えない、
ということもあり得るのではないかと、
ふと、思ったからです。
さて、災害用ビブスの場合は、自分の好きな方を選べばそれで問題はないのですが、
社会の様々な受付に置いてもらうマークが2種類ある、ということになると、
どういうことが起こるか。
大きな混乱が起こるであろうことは想像に難くない。
最悪の場合、
最悪の場合は、・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.2.16 (THU)
筆談マークについてコリさんのコメントから
余談ですが、ニシダさんのところにあった全日本ろうあ連盟が出してきた「筆談マーク」に関する協議では、ふがいないと思われないように、全難聴にはがんばってほしい。Posted by コリ at 2017年02月13日 08:43
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニシダさんの掲示板2/10より
「筆談マーク」をご存じでしょうか?ニシダツトムのそと。あそび12/10 より引用
全日本ろうあ連盟が昨年正式に導入しました。
https://www.jfd.or.jp/2016/12/01/pid15854
これに伴い私たちが慣れ親しんできた「耳マーク」の使用を控えるようにと
全日本ろうあ連盟が通達しました。
なんでかな~?
僕には理解ができません。
筆談マークのデザインは確かに分かり良いと言えば分かり良いのですが
長年に渡って全日本難聴協が耳マーク普及に取り組んできた経緯は全く反故にされても良いのだろうか?
ま、だからといって今まで耳マークの意義を訴えて各施設や店舗に置いて頂いていることでしす、
これからも耳マークを多いに広めて行きたいと思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
この件について、気にかかっていたのですが・・・。
全難聴の耳マークは、すぐれた図案ですが、かなり抽象的です。、
聾者にとっては理解しづらいのではないかな?
全ろう連の図案は、手話単語の「筆談」のイラストそのままのもの。
聾者にとっては、わかりやすい。
聾文化と難聴者文化の違い、というようなことは、?
というようなことも、考えました。
だからといって、このたびの全ろう連の、一方的な進め方には
勿論、私も納得できませんが。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生臭坊主
筆談マーク、 結局、商業マークと考えるべきかPosted by 生臭坊主 at 2017年02月16日 08:44
トランプが言っているようにお金さえ出せば何でもオッケーという意味か?
何だろう
マークの後ろにある合理的配慮とはなんだろうか
紙と鉛筆をいつも用意してあるのか
それとも音声入力でき文字を表示して目で見ることができるるものがあるのか
何なのかわかりません
このように 考えている次第であります音声は読み取れません、聞き取れません、
よってキーボード入力よりこの方が文章を書きやすいと思いますが、いかがでしょか?
筆談マーク→仏壇マークなど
誤変換もあるけれどなかなか面白いコピペばっかでごめん
日本語音声入力ガ面白いはははは
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
全日本ろうあ連盟の文書には、次のように書いてあります。
わたしたちろう者、難聴者、中途失聴者(以下、ろう者等)にとり、コミュニケーションバリアの問題は永遠の課題です。生活のあらゆる場面では聞こえる人とのコミュニケーション手段は音声が基本です。ろう者等は音声に代わる、視覚的な手段でのコミュニケーション方法、手話や筆談が必要です。
近年、手話やろう者等への理解は徐々に広がり、役所や公共施設の窓口等で筆談や手話で対応してもらえる例も見られます。ろう者等にとって「筆談で対応できる」「手話で対応できる」ことが一目でわかると、安心して公共施設等を利用することができます。
そこで、全日本ろうあ連盟は誰にでも一目でコミュニケーション手段のわかる「手話マーク」・「筆談マーク」を策定しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
みみばあちゃん
久々のコメントになりました。Posted by みみばあちゃん at 2017年02月16日 10:30
筆談マークと耳マークの違いは大きいですね。
筆談マークはそれこそ筆談の配慮を求める、配慮しますだけかと。
耳マークは筆談だけでなく合理的配慮を求めやすいマークと言えるのではないでしょうか。
筆記お願いします。
口元を見ながら理解しますからマスクを外してください。
ユックリはっきりお話ください
等々何でも良い訳です。
大きな違いは、難聴者は声に出して配慮を求められるが、ろう者の方々は発声できない方もいらっしゃるので手話の分からない方には筆談で配慮を求めなければならないこと、かな。
筆談マークがあれば難聴者も大丈夫とはなりません!
筆談だけを求めるのではありませんから。
手話マークだけに留めていただきたいです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニシダ
「耳マーク・筆談マーク・手話マーク」のどれかが良いという発想で異議を申し立てている訳ではなく、Posted by ニシダ at 2017年02月16日 10:31
「筆談マーク・手話マーク」を策定した経緯に
その場にもう一方の当事者である中途失聴・難聴者の意見が反映されていなかったことが
今回全難協が全日ろう連に「話し合い」をと訴えているのです。
障がい者権利条約批准〜障がい者差別解消法への取り組みの中で提唱されてきたのは
「私たちのことを私たち抜きで決めないで下さい」を合い言葉に取り組んできていたはずです。
僕が違和感と疑問に感じたことは正しくこの「私たち抜き・・・」の部分なのです。
「耳マーク・筆談マーク・手話マーク」は、聴障者にとっては必要な支援に繋がる重要なサインだと僕も思います。
これらのサインの普及にはおおいに賛同しますし、
及ばずながらも普及の一助が出来ればとも思っています。
洩れ伝わってきた話しでは(あくまでも正式な話しではなく噂の類だと思いますが)「筆談マーク・手話マーク」があれば「耳マーク」はもう必要ないだろう・・・使わないようにしていっても良いのではないか・・・らしい話しが流れてきました。
世間的には聴覚障がい者問題として取り上げる時は
いつもろう者を対象にしている感が強いですが、
ここでもう一歩前に進め
聴覚障がい者には中途失聴・難聴者と盲ろう者もいるのだと言うことを
ろう者問題を語ると同じように同列に固有の問題を併記して欲しいと願って止みません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生臭坊主
これだ ↓↓Posted by 生臭坊主 at 2017年02月16日 13:31
http://www.wheel-to-wheel.com/mimimark.htm
直虎ブームで炎上商法 ?
便乗商法が盛んなので
早とちりしちゃったなー
ROKU先生はカードを首からさげた
先駆者だったのですね。
耳カードに代わりキャラクターにして売りまくるのだ。(笑)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
昨日、要約筆記通訳依頼のため障害福祉課に行きました。Posted by コリ at 2017年02月16日 17:20
前回は、透明なデスクマットの間に耳マークカードが置かれていました。
ところが耳マークカードが消えていて、代わりに、
カードくらいの大きさの黄色い紙の上に「筆談してください。はっきり口元を見せて話してください。」の文字。
「耳マークは?」と聞いたのですが、係りが新しい方だったので、「さ~??」
「筆談マーク」もありませんでしたが。
今度、聞いてみようと思っています。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ROKU
貴重な書き込みをたくさんいただきました。
ありがとうございました。


これは、災害避難所用のビブスです。塩尻では2種類作りました。
聾者は、たいがい、「聞こえません」の方を選択しし、
難聴者は、たいがい、「耳が不自由です」の方を選択しています。
当初は「聞こえません」一本であったのですが。
難聴者側から、「表現が常識外れだ」という意見が出て、
「耳が不自由です」が加えられた。
ところが、聾者は、
「耳が不自由」という表現は、ピンとこない」
「聞こえるのか聞こえないのか、はっきり表現しないとわからない」
と仰る。その結果二本立てとなった。
聾者のみなさんは、婉曲的な、あるいは抽象的な表現は苦手のようです。
それがいけない、というのではなく、
それが「ろう文化」であると私は理解しております。
そういう意味で、「耳マーク」は、聾者にとって、、なにか不思議なマークにしか見えない、
ということもあり得るのではないかと、
ふと、思ったからです。
さて、災害用ビブスの場合は、自分の好きな方を選べばそれで問題はないのですが、
社会の様々な受付に置いてもらうマークが2種類ある、ということになると、
どういうことが起こるか。
大きな混乱が起こるであろうことは想像に難くない。
最悪の場合、
最悪の場合は、・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.2.16 (THU)
2016年07月08日
筆談ボード(2)
昨日(2016.7.6)の記事から(要旨)
 100円ショップで購入できる材料を用いた手作りの筆談ボードである。
100円ショップで購入できる材料を用いた手作りの筆談ボードである。
地元の要約筆記サークルと、難聴者の有志が、
毎年毎年、作成している。
難聴者は実費でわけてもらえる。
 裏側には、マーカーとイレイサー(eraser)、を入れておくための、
裏側には、マーカーとイレイサー(eraser)、を入れておくための、
ポケットが付いている。
イレイサーにはヒモが付ついている。
塩尻の難聴者の会の者は、これを持っている。
健聴者の方に使っていただくためであり、
難聴者同士での、必須のコミュニケーション手段である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪コメント≫
コリ
私も持ってます
私のは二つ折できて、メモ用紙もついているものです。
マーカーを入れる所がついてないので、忘れてばかり・・・
ついメモ用紙の方を使ってしまいます。
それだと「あ~~こんなこと話したんだ。」と思い出すことができるんですけど、
用紙がすぐになくなってしまいます。
そうそう、やっぱり、「手話はやらない。」と固い決意の方もおいでですし、
見ていると、難聴者同士が手話で話が通じるということもないようですから、
ボードやメモ用紙は欠かせません。
2016/07/07 13:26
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
健聴者とのコミュニケーションで、こういう筆談具を使うのは効果的です。
筆談用具は、肢体不自由者における車椅子、
視力障碍者における白杖などとと同じで、
健聴者の方も(我々の障害を)「目で見てわかる」形である。
、
なお、巷(ちまた)に、マグネットを利用した「筆談器」が出回っておりますが、
手づくりの、これが一番いい。 (※)
なによりも、これを作成していただいている支援者の方々の、「心」が伝わってきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※ 筆談は白地のボード(または白い紙)に黒い字で
過去ログ(2016.1.15記事)から(要旨)
あれも、その操作の面白さの方に注意が分散されてしまい、
切羽詰まっての筆談には、なんだかなあ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
「見えない段差」を見えるようにする道具ですね。
難聴者の会では健聴者もボードをもって話しかけてくれるので、
会以外で健聴者と話すときは持って行ったことがなかったのです。
これからは持っていくようにしたいです。
Posted by コリ at 2016年07月08日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
この筆談ボードは、難聴者同士の場合には大活躍をするわけですが、
健聴者とのコミュニケーションの場合には、、これに文字が書かれる機会は、
j実際には、あまりありません。
まずは、役所などで、「書いてください」と、このボードをつきだしても、
たいがいの場合、職員は、役所に備え付けのメモ用紙をお使いになる。
駅や、お店などでも、決まって、備え付けのメモ用紙が使われる。
それはそれで良いのであって、
対応する側のマナーが良いということです。
でも、そういうときでも、これを相手に見せつける、
見せつけること自体に意義があると思います。
「ああ、難聴者は、こういうものを使っているんだなあ」
と思わせる、
健聴者に気付いていただく、
そこに意義がある。
これこそ、コリさんのご指摘のように
「見えない段差」を「見えるようにするための」、
強力なアイテムです。
難聴者のとるべき、具体的な行動であると、私は思っています。
・・・・・・・・・・・
追伸 このボードが健聴者によって実際に使われ、そこに文字が書かれるという機会は
例えば、道を尋ねられた場合。
えんぱーく付近で、「長野銀行どこですか」と尋ねられたことが、複数回あります。
ボードには、
「長野銀行」
と書かれるだけだが、それだけで、
何を尋ねられているのかは、わかります。。
そういう、とっさの場合には、このボードが活躍します。
最近に知ったのですが、
昔は、現在のえんぱーくの近くに長野銀行があったみたいですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.7.8 (FRI)
地元の要約筆記サークルと、難聴者の有志が、
毎年毎年、作成している。
難聴者は実費でわけてもらえる。
ポケットが付いている。
イレイサーにはヒモが付ついている。
塩尻の難聴者の会の者は、これを持っている。
健聴者の方に使っていただくためであり、
難聴者同士での、必須のコミュニケーション手段である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪コメント≫
コリ
私も持ってます
私のは二つ折できて、メモ用紙もついているものです。
マーカーを入れる所がついてないので、忘れてばかり・・・
ついメモ用紙の方を使ってしまいます。
それだと「あ~~こんなこと話したんだ。」と思い出すことができるんですけど、
用紙がすぐになくなってしまいます。
そうそう、やっぱり、「手話はやらない。」と固い決意の方もおいでですし、
見ていると、難聴者同士が手話で話が通じるということもないようですから、
ボードやメモ用紙は欠かせません。
2016/07/07 13:26
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
健聴者とのコミュニケーションで、こういう筆談具を使うのは効果的です。
筆談用具は、肢体不自由者における車椅子、
視力障碍者における白杖などとと同じで、
健聴者の方も(我々の障害を)「目で見てわかる」形である。
、
なお、巷(ちまた)に、マグネットを利用した「筆談器」が出回っておりますが、
手づくりの、これが一番いい。 (※)
なによりも、これを作成していただいている支援者の方々の、「心」が伝わってきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※ 筆談は白地のボード(または白い紙)に黒い字で
過去ログ(2016.1.15記事)から(要旨)
・・・・(ドコモショップでスタッフが)私が出したメモ用紙には目もくれないで、最近では、タブレットに筆談アプリが入っている。、
いきなり、備え付けの筆談ボードに説明を書きはじめた。(中略)
せっかく速く書いてくれて、字もきれいなんだけど、
黒地のボードなので、
書いている最中には、こちらからは全然読めない。
2~3行を書いては、そのボードをこちら向きにしてくれるのだが、
室内照明が反射して、実に読みにくい。
ボードの角度を調節したりして、大変苦労した。
これは多分、会社の方針で、
「難聴者にはこの筆談ボードで対応せよ」
というルールがあるのだろう。
会社とすれば、なにか、障害者フレンドリーな、とても親切な、
よいことをやっているように思っているに違いない。
最近、要約筆記者の中にも、こういうものを持っていらっしゃる方がいる。
ハッキリ申し上げて、市販の筆談ボードはダメである。
遊び感覚で使ったりするには、どうということはないが、
商談とか、大事な場面では、この機種はダメである。
ままごとの玩具みたいな商品を「筆談ボード」などと称して売りつける偽善のようなことは、
即刻、止めてもらいたい。
筆談は白地のボード(または白い紙)に黒い字で! 2016.1.15
あれも、その操作の面白さの方に注意が分散されてしまい、
切羽詰まっての筆談には、なんだかなあ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
「見えない段差」を見えるようにする道具ですね。
難聴者の会では健聴者もボードをもって話しかけてくれるので、
会以外で健聴者と話すときは持って行ったことがなかったのです。
これからは持っていくようにしたいです。
Posted by コリ at 2016年07月08日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
この筆談ボードは、難聴者同士の場合には大活躍をするわけですが、
健聴者とのコミュニケーションの場合には、、これに文字が書かれる機会は、
j実際には、あまりありません。
まずは、役所などで、「書いてください」と、このボードをつきだしても、
たいがいの場合、職員は、役所に備え付けのメモ用紙をお使いになる。
駅や、お店などでも、決まって、備え付けのメモ用紙が使われる。
それはそれで良いのであって、
対応する側のマナーが良いということです。
でも、そういうときでも、これを相手に見せつける、
見せつけること自体に意義があると思います。
「ああ、難聴者は、こういうものを使っているんだなあ」
と思わせる、
健聴者に気付いていただく、
そこに意義がある。
これこそ、コリさんのご指摘のように
「見えない段差」を「見えるようにするための」、
強力なアイテムです。
難聴者のとるべき、具体的な行動であると、私は思っています。
・・・・・・・・・・・
追伸 このボードが健聴者によって実際に使われ、そこに文字が書かれるという機会は
例えば、道を尋ねられた場合。
えんぱーく付近で、「長野銀行どこですか」と尋ねられたことが、複数回あります。
ボードには、
「長野銀行」
と書かれるだけだが、それだけで、
何を尋ねられているのかは、わかります。。
そういう、とっさの場合には、このボードが活躍します。
最近に知ったのですが、
昔は、現在のえんぱーくの近くに長野銀行があったみたいですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.7.8 (FRI)
2016年07月05日
私の筆談ボード
≪私の筆談ボード≫

100円ショップで購入できる材料を用いた、手作りの筆談ボードである。
地元の要約筆記サークルと、難聴者の有志が、、
もう10年以上も前から、毎年毎年、作成している。
難聴者は実費でわけてもらえる。
写真のボードは、5年ほど前のものである。

裏側には、マーカーと消しゴム、もとい、黒板消し、
もとい、えーと、なんていうのかな、英語で言うとイレイサー(eraser)、
それを入れておくための、ポケットが付いている。
かわいいね。
イレイサーにはヒモが付ついている。
高齢者だからな、
失くさないように!
私は、いつもこれを持ち歩いている。
塩尻の難聴者の会の者は、みなさん、これを持っている。
健聴者の方に使っていただくためである。
難聴者同士では、お互い、手話のような身振りをする者が多いが、、
必要に応じて、キーワードなど、これに書きます。
手話を全然やらない、という方もいらっしゃる。
このミニボードが大活躍する!。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
私も持ってます
私のは二つ折できて、メモ用紙もついているものです。
マーカーを入れる所がついてないので、忘れてばかり・・・
ついメモ用紙の方を使ってしまいます。
それだと「あ~~こんなこと話したんだ。」と思い出すことができるんですけど、
用紙がすぐになくなってしまいます。
そうそう、やっぱり、「手話はやらない。」と固い決意の方もおいでですし、
見ていると、難聴者同士が手話で話が通じるということもないようですから、
ボードやメモ用紙は欠かせません。
2016/07/07 13:26
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.7.5 (TUE)
100円ショップで購入できる材料を用いた、手作りの筆談ボードである。
地元の要約筆記サークルと、難聴者の有志が、、
もう10年以上も前から、毎年毎年、作成している。
難聴者は実費でわけてもらえる。
写真のボードは、5年ほど前のものである。
裏側には、マーカーと消しゴム、もとい、黒板消し、
もとい、えーと、なんていうのかな、英語で言うとイレイサー(eraser)、
それを入れておくための、ポケットが付いている。
かわいいね。
イレイサーにはヒモが付ついている。
高齢者だからな、
失くさないように!
私は、いつもこれを持ち歩いている。
塩尻の難聴者の会の者は、みなさん、これを持っている。
健聴者の方に使っていただくためである。
難聴者同士では、お互い、手話のような身振りをする者が多いが、、
必要に応じて、キーワードなど、これに書きます。
手話を全然やらない、という方もいらっしゃる。
このミニボードが大活躍する!。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
私も持ってます
私のは二つ折できて、メモ用紙もついているものです。
マーカーを入れる所がついてないので、忘れてばかり・・・
ついメモ用紙の方を使ってしまいます。
それだと「あ~~こんなこと話したんだ。」と思い出すことができるんですけど、
用紙がすぐになくなってしまいます。
そうそう、やっぱり、「手話はやらない。」と固い決意の方もおいでですし、
見ていると、難聴者同士が手話で話が通じるということもないようですから、
ボードやメモ用紙は欠かせません。
2016/07/07 13:26
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.7.5 (TUE)
2016年07月02日
難聴者の筆談について
≪四季の万華鏡≫
夏の雲

JR 塩尻駅前 Photo 2016.7.1

高ボッチ上空の雲 えんぱーく から
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
☆ 筆談ということがわからなくなりました。
難聴者同士が筆談(身振り、指さし、簡単な手話を含む)することはわかるんですけど、
相手が健聴者の場合(これが一番多いのですが)、
書くのは健聴者で、難聴者は音声で答える。これも筆談なんでしょうか。
辞書によると、「文字や文を紙などに記して意志を伝え合うこと」となっています。
Posted by コリ at 2016年07月02日 08:51
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
難聴者の「筆談」について
<コリさんからの質問。>
「いい質問ですねえ」(池上さん!)
ちなみに、池上さんは信州人ですよ。
池上さんが知事とか大臣をやれば、面白いだろうね。
議員の(血相変えた)質問に対して
「いい質問ですねえ・・・」とやれば、議会も和むだろう。
(閑話休題)
辞書にある「筆談」の定義には確かにあてはまらない。
しかし、コリさんの仰るように、
「相手が健聴者の場合これが一番多い」。
のが、実態です。
この実態にあてはまる言葉が、存在しないわけですね。
「身振り、指さし、簡単な手話のようなもの」が入って、
それで通じてしまう場合はそれでよいわけですが、通じない場合はどうするか。
手話の方々は、あくまで手話。最後まで手話です。
難聴者の場合には、最終手段として「書いてもらう」。
難聴者のコミュニケーションは、身振りや手話のようなことをやっているときでも、
時々、通じなくなって、単語の一語、漢字一字で、また、前後がつながって、
再び、身振りに戻ったりする。
つまり、難聴者のコミュニケーションでは、
文字によるコミュニケーションが、そのベースとなっている。
難聴者のコミュニケーションの実態を表す用語 例えば「半筆談」とか、
そういう用語が(いまのところ)存在しないかぎり、
不本意ではあるが「筆談」という言葉を広義に解釈して使用する以外にない、
つまり、用語が、つまり一般の辞書が、実態に追いついていない。
トータルコミュニケーションという用語を使えば、
より正確な表現になるかもしれませんね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
お返事ありがとうございます。
ちょっと質問の仕方がまずかったようです。すみません、もう一度書かせてください。
・難聴者同士のコミュニケーション
お互いに書き合うので、これを筆談と呼ぶのはわかります。筆談にジェスチャー、口語、簡単な手話等を伴うので、トータルコミュニケーションと呼ばれることもわかります。
筆談ホステスの場合もお客は書いて伝え、ホステスも書いて伝えるので、この場合も筆談というのはわかります。
・難聴者と健聴者のコミュニケーション(要約筆記者や難聴者の会で健聴者は除く)についてお聞きしたかったのです。
このとき、中に入れないという見えない段差、あるいは書いてもらうという後ろめたさを感じるのではないでしょうか。
難聴者同士と話すのは難聴者の会くらいで、それ以外は健聴者と話す方が多いのです。
市役所職員を例にあげると、最初から最後まで、話しながら文字で伝えます。身振りも、手話もありません。こちらは音声で答えるのみです。
健聴者は一般的に身振りとか表情を変えるとかはしないのではないでしょうか。書くだけです。
こんな風に、一方的に書き、一方的に音声で答える会話も筆談と言うのだろうか。
いままでは筆談だと思っていましたが。
音声では理解できない人には、自分のことばを筆記に直して伝えています。
長くなりました。よけいにわかりにくくなってしまったかもしれません。
Posted by コリ at 2016年07月02日 19:59
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
私のreplyが、じつは、ラーメン屋の店員の対応とかを想定してのものしたので、
ちょっと、ピント外れだったかな。

JR広丘駅。
広丘駅だけでなく、塩尻駅、村井、南松本、松本駅)にも出ております。
JR全域かも。
このような掲示は、
「こちらが一方的に音声でしゃべり、駅員が一方的に書く」
ということが、想定されて出ているわけで、
こちらが書かなければ応じない、なんて言うことは、絶対にありえない。。
実際に私も、身体障害者割引を利用するときなど、
一方的にしゃべりまくっております。
※ ただし、「うしろめたさ」はあるので、旅行日程の基本的データは
あらかじめ紙に書いて持っていくが、
別にそうしなくてはならないというわけでもない。
難聴者のREAD ONLYの「筆談(?!)は
世間一般に「(広義の)筆談」として認められていると思います。、
難聴者と健聴者との筆談は、
実は難聴者本人は
辞書の定義そのままの筆談は、していない
それが、健聴者とともに暮らしている我々の日常生活の
ほとんど100パーセントといっていい。
実態は、まさに、コリさんの仰るとおりですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
全く偶然ですが、(♪ 突然 偶然 それとも 必然)
本日のニシダさんの掲示板に、難聴者の手話という角度から、
難聴者は「日本語がベース」であること述べておられます。
→ http://www.number7.jp/bbs/nishiart/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.7.2 (SAT)
コリ
再度、お返事ありがとうございました。とてもよくわかりました。^_^)
健聴者との会話では難聴者はRead Onlyの筆談を使うと以前書いておいでだったのを、すっかり忘れていました。
ところで、私のように単純思考では、ろう者もまた「手話ユビキタス」を望むのは当然だと思うのですが,
そのあたりのことを、いつか機会があったら教えてください。
Posted by コリ at 2016年07月03日 08:
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
問題提起してただき、ありがとうございました。
聾者もまた、・・・・については、いずれ、別記事で
2016.7.3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
夏の雲
JR 塩尻駅前 Photo 2016.7.1
高ボッチ上空の雲 えんぱーく から
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
☆ 筆談ということがわからなくなりました。
難聴者同士が筆談(身振り、指さし、簡単な手話を含む)することはわかるんですけど、
相手が健聴者の場合(これが一番多いのですが)、
書くのは健聴者で、難聴者は音声で答える。これも筆談なんでしょうか。
辞書によると、「文字や文を紙などに記して意志を伝え合うこと」となっています。
Posted by コリ at 2016年07月02日 08:51
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
難聴者の「筆談」について
<コリさんからの質問。>
難聴者同士が筆談(身振り、指さし、簡単な手話を含む)することはわかるんですけど、
相手が健聴者の場合(これが一番多いのですが)、
書くのは健聴者で、難聴者は音声で答える。これも筆談なんでしょうか。
「いい質問ですねえ」(池上さん!)
ちなみに、池上さんは信州人ですよ。
池上さんが知事とか大臣をやれば、面白いだろうね。
議員の(血相変えた)質問に対して
「いい質問ですねえ・・・」とやれば、議会も和むだろう。
(閑話休題)
辞書にある「筆談」の定義には確かにあてはまらない。
しかし、コリさんの仰るように、
「相手が健聴者の場合これが一番多い」。
のが、実態です。
この実態にあてはまる言葉が、存在しないわけですね。
「身振り、指さし、簡単な手話のようなもの」が入って、
それで通じてしまう場合はそれでよいわけですが、通じない場合はどうするか。
手話の方々は、あくまで手話。最後まで手話です。
難聴者の場合には、最終手段として「書いてもらう」。
難聴者のコミュニケーションは、身振りや手話のようなことをやっているときでも、
時々、通じなくなって、単語の一語、漢字一字で、また、前後がつながって、
再び、身振りに戻ったりする。
つまり、難聴者のコミュニケーションでは、
文字によるコミュニケーションが、そのベースとなっている。
難聴者のコミュニケーションの実態を表す用語 例えば「半筆談」とか、
そういう用語が(いまのところ)存在しないかぎり、
不本意ではあるが「筆談」という言葉を広義に解釈して使用する以外にない、
つまり、用語が、つまり一般の辞書が、実態に追いついていない。
トータルコミュニケーションという用語を使えば、
より正確な表現になるかもしれませんね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
お返事ありがとうございます。
ちょっと質問の仕方がまずかったようです。すみません、もう一度書かせてください。
・難聴者同士のコミュニケーション
お互いに書き合うので、これを筆談と呼ぶのはわかります。筆談にジェスチャー、口語、簡単な手話等を伴うので、トータルコミュニケーションと呼ばれることもわかります。
筆談ホステスの場合もお客は書いて伝え、ホステスも書いて伝えるので、この場合も筆談というのはわかります。
・難聴者と健聴者のコミュニケーション(要約筆記者や難聴者の会で健聴者は除く)についてお聞きしたかったのです。
このとき、中に入れないという見えない段差、あるいは書いてもらうという後ろめたさを感じるのではないでしょうか。
難聴者同士と話すのは難聴者の会くらいで、それ以外は健聴者と話す方が多いのです。
市役所職員を例にあげると、最初から最後まで、話しながら文字で伝えます。身振りも、手話もありません。こちらは音声で答えるのみです。
健聴者は一般的に身振りとか表情を変えるとかはしないのではないでしょうか。書くだけです。
こんな風に、一方的に書き、一方的に音声で答える会話も筆談と言うのだろうか。
いままでは筆談だと思っていましたが。
音声では理解できない人には、自分のことばを筆記に直して伝えています。
長くなりました。よけいにわかりにくくなってしまったかもしれません。
Posted by コリ at 2016年07月02日 19:59
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
私のreplyが、じつは、ラーメン屋の店員の対応とかを想定してのものしたので、
ちょっと、ピント外れだったかな。

JR広丘駅。
広丘駅だけでなく、塩尻駅、村井、南松本、松本駅)にも出ております。
JR全域かも。
このような掲示は、
「こちらが一方的に音声でしゃべり、駅員が一方的に書く」
ということが、想定されて出ているわけで、
こちらが書かなければ応じない、なんて言うことは、絶対にありえない。。
実際に私も、身体障害者割引を利用するときなど、
一方的にしゃべりまくっております。
※ ただし、「うしろめたさ」はあるので、旅行日程の基本的データは
あらかじめ紙に書いて持っていくが、
別にそうしなくてはならないというわけでもない。
難聴者のREAD ONLYの「筆談(?!)は
世間一般に「(広義の)筆談」として認められていると思います。、
難聴者と健聴者との筆談は、
実は難聴者本人は
辞書の定義そのままの筆談は、していない
それが、健聴者とともに暮らしている我々の日常生活の
ほとんど100パーセントといっていい。
実態は、まさに、コリさんの仰るとおりですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
全く偶然ですが、(♪ 突然 偶然 それとも 必然)
本日のニシダさんの掲示板に、難聴者の手話という角度から、
難聴者は「日本語がベース」であること述べておられます。
そして、最も肝心で重要な事は、
難聴者の主言語は【日本語】だと言う事。
聞こえなかった、聞き分けられなかった、手話が読みとれなかった・・・
最後の砦は、【筆談】になるのです。
→ http://www.number7.jp/bbs/nishiart/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.7.2 (SAT)
コリ
再度、お返事ありがとうございました。とてもよくわかりました。^_^)
健聴者との会話では難聴者はRead Onlyの筆談を使うと以前書いておいでだったのを、すっかり忘れていました。
ところで、私のように単純思考では、ろう者もまた「手話ユビキタス」を望むのは当然だと思うのですが,
そのあたりのことを、いつか機会があったら教えてください。
Posted by コリ at 2016年07月03日 08:
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
問題提起してただき、ありがとうございました。
聾者もまた、・・・・については、いずれ、別記事で
2016.7.3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016年06月14日
筆談器は、あなたが使うんです
2016.6.14
 先週末、塩尻市福祉課障がい係から、
先週末、塩尻市福祉課障がい係から、
「塩尻市役所の市民課にも筆談器が入りました」
という趣旨の、聴覚障害者あてのメールをいただいた。
いよいよ、「合理的配慮」が始まったんだな!
(^-^)
本日、塩尻市役所へ行き、
インフォメーションで身分を明らかにして、、
私は塩尻市の難聴者を代表して来ていることを伝え、
「筆談ボードを入れたそうですが」
と質問した。
インフォメーションの受付嬢が、
「市民課です」
と、ご親切にも市民課まで案内してくださった。
(実際には、インフォメーションと市民課は、目と鼻の先だが)
そこまではよかった。
市民課の窓口で。
「筆談器を入れたそうですが、見せて頂けますか」
と尋ねたところ、職員(女性)が、なぜか、うろたえて、
「ちょっと待って!」
やがて、奥の方から、得得としたお顔で、
筆談ボードを持ってきた。
そして、それを私に手渡して
さあ、どうぞ !
筆談ボードは私(聴覚障害者)が使うものであると、
そう思い込んでいるご様子。
あのね、それ、違うんですよ。
私はこうして普通に話すことができているじゃないですか。
でも、私は聞こえないんです。
ですから、これは、
あなたが使うんです !
(註) 筆談ボードそのものは、私の嫌いな「黒地」のヤツだが、
まあ、それは別の問題であって、この際は問題にしないでおこう。
とにかく、こういうものを用意して「書きますよ」という「心」を示していただくことは
まことにありがたい。小口市長殿に感謝します。
でも、ろう者と難聴者のちがいぐらいは、職員に教えといてもらわなくっちゃ。
2016.6.14 (TUE)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<この記事へのコメント>
旅人
お~い、山田君
ROKUさんに
座布団10枚やって!
Posted by 旅人 at 2016年06月14日 23:24
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
別に、意地悪されたということではなく、対応職員はとても親切たっだ。
おそらく、荷を開けたばかりの筆談ボードを目の前にして、
一瞬、戸惑い、錯覚した! というところだろう。
市民課の名誉のために、過去記事(2011/02/08)を付記いたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
「ありがとう」人間関係を滑らかにする潤滑油ですね。
サンキュー、
ダンケ、
メルシー、
テレマカシー
コップンカップ、
シェイシェイ
などいろいろと覚えたが
いろんな場面で使うことが多かったのは イギリスやアイルランド、
微笑みの国のタイランドでした
日本では、たわいの無い事でも紳士の国では 非常に、よく使われます。
一読、ありがとう(^^♪
2016/06/15 08:27:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
テレマカシー
コップンカップ
??
アジア方面の ??
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
市民課の職員の対応に笑ってしまいました。
旅人さん、ROKUさんが笑点が好きなのをちゃんと覚えてらして、
見事なコメント!旅人さんのコメントには毎回うなっています。
私も、「面倒だな~」「イヤだな~」と思いながらやっていたのに、
「ありがとう。」の一言で、なんか報われた気持ちになります。
それなのに、考えてみると、市役所職員の筆談に対してとか、
難聴者の会が終わった後に、要約筆記の方々に、
言葉でお礼を言ったことがないような気がする。
心の中では感謝しているけれど、あまりにも自然なサポートだから・・
私の市でも筆談器入ったのかしら?これまでは相手が用意してくれた紙でした。 コリ
2016/06/15 09:56
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
ご指摘の通りで、私は怒っているわけではなく、
職員の、とっさの対応が面白いと思って書いただけです。
私の文章のニュアンスを、旅人さんが、的確に、うまくとらえてくださった。
文章で表現すると、「オチ」のある小噺ふうですが、
実際には一瞬のアクシデントであり、
(職員も)気が付いて、双方、笑った。
そのあと、件の筆談ボードの「初おろし」で、対応してくださったのは勿論です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
テレマカシーは
インドネシアにマレーシアと
近年、日本でも多く見かけるようになったレジのおねーさんとか
介護士で大変だから
ちょっとしたことでも、最後に付け加えてあげると
嬉しい微笑みが拝めます。
タイランドは昔、日本の同盟国で親日な人が多い
タイ人に蓮の花のつぼみのように両手を合わせて
コップンカップと言えば
飛び切り極上の微笑みが返ってきます。
雑学でした(^^)v
Posted by 旅人 at 2016年06月15日 12:21
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
「テレマカシー」は、老後に役立つ必須単語だね。
旅人さん、すごい !
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
あやつの辞書に「ありがとう」が載っていたとは・・・
でも、思ったな。
食い逃げ、摘み食いする人が あとから言っても白々しいってもんだ
私も大きなことは言えないが
形式であろうが その場で感謝の意を表すのは大事だし、大事にしたい。
読んで頂き感謝(*^_^*) 旅人
2016/06/16 05:41:
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
追記 2017.8.18
現在ではUDtalkもあり、職員が臨機応変に、使いやすい手段で、
コミュニケーションができるようになっている。
なお、ろう者の場合には、隣接の保健福祉センター内の福祉課に
設置通訳者が配置されているので、
市民課まで(歩いて)きていただいて、手話で対応していただける。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「塩尻市役所の市民課にも筆談器が入りました」
という趣旨の、聴覚障害者あてのメールをいただいた。
いよいよ、「合理的配慮」が始まったんだな!
(^-^)
本日、塩尻市役所へ行き、
インフォメーションで身分を明らかにして、、
私は塩尻市の難聴者を代表して来ていることを伝え、
「筆談ボードを入れたそうですが」
と質問した。
インフォメーションの受付嬢が、
「市民課です」
と、ご親切にも市民課まで案内してくださった。
(実際には、インフォメーションと市民課は、目と鼻の先だが)
そこまではよかった。
市民課の窓口で。
「筆談器を入れたそうですが、見せて頂けますか」
と尋ねたところ、職員(女性)が、なぜか、うろたえて、
「ちょっと待って!」
やがて、奥の方から、得得としたお顔で、
筆談ボードを持ってきた。
そして、それを私に手渡して
さあ、どうぞ !
筆談ボードは私(聴覚障害者)が使うものであると、
そう思い込んでいるご様子。
あのね、それ、違うんですよ。
私はこうして普通に話すことができているじゃないですか。
でも、私は聞こえないんです。
ですから、これは、
あなたが使うんです !
(註) 筆談ボードそのものは、私の嫌いな「黒地」のヤツだが、
まあ、それは別の問題であって、この際は問題にしないでおこう。
とにかく、こういうものを用意して「書きますよ」という「心」を示していただくことは
まことにありがたい。小口市長殿に感謝します。
でも、ろう者と難聴者のちがいぐらいは、職員に教えといてもらわなくっちゃ。
2016.6.14 (TUE)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<この記事へのコメント>
旅人
お~い、山田君
ROKUさんに
座布団10枚やって!
Posted by 旅人 at 2016年06月14日 23:24
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
別に、意地悪されたということではなく、対応職員はとても親切たっだ。
おそらく、荷を開けたばかりの筆談ボードを目の前にして、
一瞬、戸惑い、錯覚した! というところだろう。
市民課の名誉のために、過去記事(2011/02/08)を付記いたします。
市役所市民課で(新規に)印鑑登録ならびに印鑑登録証明書の交付を申請した。
市民課のカウンターには数名の職員が並んでいらっしゃり、向かって一番左が受付係の職員。
受付係(女性)に申請用紙を提出。
身体障害者手帳を提示しながら、自分が難聴者であること、
したがって筆談で対応してほしいということを、手話を交えて伝えた。
受付係は申請用紙を点検し、「わかりました、しばらくあちらでお待ちください」
と、これは筆談でも手話でもなかったが、わかりやすいジェスチャーで、
少し離れた右後方の、待ち席(長椅子)を指差した。
普通の場合は、受理された書類が次々と右へ回されて処理され、
最終的には一番右の職員から、次々に名前を呼ばれる。
長椅子に座って待っていると、正面から名前を呼ばれるということになる。
私は目の前で名前を呼ばれてもわからないから、こういう場合、
自分の提出した書類が次々にわたされていくのを、目で追跡。
様子を見ていたら、さきほど受け付けてくださった職員が、
右の席の職員(男性)と受付係(の位置)を交代した。
そして私の書類を持って、右へ右へと移動しながら、
次々になにやら書き込んだり押印したりしていく。
最終的にすべての処理を済ませて、チラリと私のいる方を見た。
そして、カウンター右端に設けられている職員通用口から出て、
私の方へ向かって、書類をもって歩いてくるではないか。
この対応には感激した。
「ご親切にありがとうございます」の言葉と手話が心から、
自然に出た。 2011/02/08
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
「ありがとう」人間関係を滑らかにする潤滑油ですね。
サンキュー、
ダンケ、
メルシー、
テレマカシー
コップンカップ、
シェイシェイ
などいろいろと覚えたが
いろんな場面で使うことが多かったのは イギリスやアイルランド、
微笑みの国のタイランドでした
日本では、たわいの無い事でも紳士の国では 非常に、よく使われます。
一読、ありがとう(^^♪
2016/06/15 08:27:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
テレマカシー
コップンカップ
??
アジア方面の ??
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
市民課の職員の対応に笑ってしまいました。
旅人さん、ROKUさんが笑点が好きなのをちゃんと覚えてらして、
見事なコメント!旅人さんのコメントには毎回うなっています。
私も、「面倒だな~」「イヤだな~」と思いながらやっていたのに、
「ありがとう。」の一言で、なんか報われた気持ちになります。
それなのに、考えてみると、市役所職員の筆談に対してとか、
難聴者の会が終わった後に、要約筆記の方々に、
言葉でお礼を言ったことがないような気がする。
心の中では感謝しているけれど、あまりにも自然なサポートだから・・
私の市でも筆談器入ったのかしら?これまでは相手が用意してくれた紙でした。 コリ
2016/06/15 09:56
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
ご指摘の通りで、私は怒っているわけではなく、
職員の、とっさの対応が面白いと思って書いただけです。
私の文章のニュアンスを、旅人さんが、的確に、うまくとらえてくださった。
文章で表現すると、「オチ」のある小噺ふうですが、
実際には一瞬のアクシデントであり、
(職員も)気が付いて、双方、笑った。
そのあと、件の筆談ボードの「初おろし」で、対応してくださったのは勿論です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
テレマカシーは
インドネシアにマレーシアと
近年、日本でも多く見かけるようになったレジのおねーさんとか
介護士で大変だから
ちょっとしたことでも、最後に付け加えてあげると
嬉しい微笑みが拝めます。
タイランドは昔、日本の同盟国で親日な人が多い
タイ人に蓮の花のつぼみのように両手を合わせて
コップンカップと言えば
飛び切り極上の微笑みが返ってきます。
雑学でした(^^)v
Posted by 旅人 at 2016年06月15日 12:21
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
「テレマカシー」は、老後に役立つ必須単語だね。
旅人さん、すごい !
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
今朝、ニュースを検索していたら あのドケチ都知事が都議会で言った発言の一部が目に飛び込んできました。
“発言をお許しいただきありがとうございます。一言申し上げたい。本当に都民のみなさま、都議会のみなさまにご迷惑をおかけしたことを、改めて心から陳謝したい。(中略)
あやつの辞書に「ありがとう」が載っていたとは・・・
でも、思ったな。
食い逃げ、摘み食いする人が あとから言っても白々しいってもんだ
私も大きなことは言えないが
形式であろうが その場で感謝の意を表すのは大事だし、大事にしたい。
読んで頂き感謝(*^_^*) 旅人
2016/06/16 05:41:
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
追記 2017.8.18
現在ではUDtalkもあり、職員が臨機応変に、使いやすい手段で、
コミュニケーションができるようになっている。
なお、ろう者の場合には、隣接の保健福祉センター内の福祉課に
設置通訳者が配置されているので、
市民課まで(歩いて)きていただいて、手話で対応していただける。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016年06月06日
「筆談ホステス」やっていません
長野難聴のブログより引用いたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
"書いてもらう"ことへの後ろめたさ
健聴者(A)と、
話せるけれども文字情報を必要とする聞こえない人(B)
(A)と(B)とのコミュニケーションでは、
一方に大きな負担をかけることになります。
(B)は音声で発信し、文字で受け取る・・・・
それに対して(A)は文字で発信し、音声で受け取る・・・・
この負担の”差”は、否応なく、双方に意識させられます。
難聴者が、健聴者に”書いてもらう”ことへの後ろめたさや、
負担をかけてすまないという心理は、
みんな経験していることです。
Posted by K.S 2016.6.2 (THU)
http://naganonancho.naganoblog.jp/e1931763.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
難聴者は「筆談テステス」をやっていません
いつぞやは
「筆談ホステス」
が、一世を風靡した。
斉藤りえさん、現在は、東京都北区、議員さんである。
あの方は、すごいと思う。
頭脳明晰、
お書きになる文章がしっかりしている。
とっさの会話で、あれだけ上手に、的確に、文章で表現できる、
(客の)男心をそそう、
そういう技術。
そいうことの出来る人を私は、
他に知らない。
(閑話休題)
さて、私は、筆談ホステスのようには、やっておりません。
食卓に、A5の用紙をさらに四つ折りに切った、メモ用紙をおいてあります。
私に関する話題があるときには、家族が
そのメモに書いて伝えてくれる。
その返答は、筆談ではありません。
音声でこたえている。
音声の聞こえない者が、
自分だけは、一方的に音声で伝える。
その「うしろめたさ」!
ああ、迷惑かけているナア。
と思っている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
迷惑をかけたりかけられたりするのは
日本人の愛情の表現と思いますが
どうでしょうか?
ROKUさんのご家族は
あるいは、ニシダさんの長兄や次兄にしろ
本当に迷惑だと思っているのだろうか?
田中角栄さんが
日中国交パーティーのスピーチで
中国に迷惑を掛けたと言った言葉を
中国人通訳がそのまま伝えたために
中国側が色めき立って険悪な状況になったとか・・・
かんたんに、中国を愛していますって言えばよかったんですけどね~
と、言うことで
ROKUさんの迷惑を掛けていると言う言葉は
ご家族を愛していると解釈します。
ごちそうさまでしたm(__)m
Posted by 旅人 at 2016年06月06日 12:09
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
なるほどね。
世の中ってのは、お互い、迷惑をかけあって成り立っている。
迷惑をかけていない、なんていう人だって、
酸素を吸って、CO2を出している。
人間、生きているということ自体が大迷惑なわけだ。
Posted by 六万石 at 2016年06月06日 17:09
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
齋藤りえさん(筆談ホステス)の場合とは違うと思います。
齋藤さんはご自身の伝えたいことを相手に理解してもらうための手段として、
音声言語ではなく筆談をしているので、
相手が筆談をしてくれたから、そのお返しとして筆談しているのではないと思います。
日本語を獲得してから難聴になった人は
音声言語の方が筆談よりももっと正確に相手に伝えられますから、
わざわざ筆談で応じなくてもいいと思います。
そんなことわかっているのに、あ~迷惑だろうなと思ってしまう。それは、
「もし自分だったら、筆談なんて面倒くさい・・・」
という気持ちの裏返しかもしれない。
Posted by コリ at 2016年06月06日 17:04
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.6.6 (MON)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
"書いてもらう"ことへの後ろめたさ
健聴者(A)と、
話せるけれども文字情報を必要とする聞こえない人(B)
(A)と(B)とのコミュニケーションでは、
一方に大きな負担をかけることになります。
(B)は音声で発信し、文字で受け取る・・・・
それに対して(A)は文字で発信し、音声で受け取る・・・・
この負担の”差”は、否応なく、双方に意識させられます。
難聴者が、健聴者に”書いてもらう”ことへの後ろめたさや、
負担をかけてすまないという心理は、
みんな経験していることです。
Posted by K.S 2016.6.2 (THU)
http://naganonancho.naganoblog.jp/e1931763.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
難聴者は「筆談テステス」をやっていません
いつぞやは
「筆談ホステス」
が、一世を風靡した。
斉藤りえさん、現在は、東京都北区、議員さんである。
あの方は、すごいと思う。
頭脳明晰、
お書きになる文章がしっかりしている。
とっさの会話で、あれだけ上手に、的確に、文章で表現できる、
(客の)男心をそそう、
そういう技術。
そいうことの出来る人を私は、
他に知らない。
(閑話休題)
さて、私は、筆談ホステスのようには、やっておりません。
食卓に、A5の用紙をさらに四つ折りに切った、メモ用紙をおいてあります。
私に関する話題があるときには、家族が
そのメモに書いて伝えてくれる。
その返答は、筆談ではありません。
音声でこたえている。
音声の聞こえない者が、
自分だけは、一方的に音声で伝える。
その「うしろめたさ」!
ああ、迷惑かけているナア。
と思っている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
迷惑をかけたりかけられたりするのは
日本人の愛情の表現と思いますが
どうでしょうか?
ROKUさんのご家族は
あるいは、ニシダさんの長兄や次兄にしろ
本当に迷惑だと思っているのだろうか?
田中角栄さんが
日中国交パーティーのスピーチで
中国に迷惑を掛けたと言った言葉を
中国人通訳がそのまま伝えたために
中国側が色めき立って険悪な状況になったとか・・・
かんたんに、中国を愛していますって言えばよかったんですけどね~
と、言うことで
ROKUさんの迷惑を掛けていると言う言葉は
ご家族を愛していると解釈します。
ごちそうさまでしたm(__)m
Posted by 旅人 at 2016年06月06日 12:09
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
なるほどね。
世の中ってのは、お互い、迷惑をかけあって成り立っている。
迷惑をかけていない、なんていう人だって、
酸素を吸って、CO2を出している。
人間、生きているということ自体が大迷惑なわけだ。
Posted by 六万石 at 2016年06月06日 17:09
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
齋藤りえさん(筆談ホステス)の場合とは違うと思います。
齋藤さんはご自身の伝えたいことを相手に理解してもらうための手段として、
音声言語ではなく筆談をしているので、
相手が筆談をしてくれたから、そのお返しとして筆談しているのではないと思います。
日本語を獲得してから難聴になった人は
音声言語の方が筆談よりももっと正確に相手に伝えられますから、
わざわざ筆談で応じなくてもいいと思います。
そんなことわかっているのに、あ~迷惑だろうなと思ってしまう。それは、
「もし自分だったら、筆談なんて面倒くさい・・・」
という気持ちの裏返しかもしれない。
Posted by コリ at 2016年06月06日 17:04
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.6.6 (MON)
2016年03月09日
♪春は忍び寄りぬ
於 松本市 寿(ことぶき) 赤木 3/8
♪ 君亡き里にも
春は忍び寄りぬ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪最近のこと・あれこれ≫
☆ 図書館で
えんぱーく(塩尻市図書館)へ行くと
職員が、受付で、一生懸命に
「こんにちは」」
「ありがとう」
の手話をなさる。
近く、手話言語条例が県議会で採決される。
そのせいかもしれないが、職員は、
簡単な挨拶程度の手話の研修をうけているようだ。
職員がせっかく手話を習っても、
図書館を利用する聴障者がいなければ
張り合いがなかろう。
ろう者も、もっと図書館を利用すべきである。
というわけで私は、
これからも
せっせと図書館を利用しようと思っている。 3/7
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ 道を教える
塩尻駅の近く、松田眼科の前で
年配の女性に呼び止められた。
何を言っているかわからないので、私は、
耳が不自由であることを告げて自転車を降り、
手製の筆談ボードを出して、
「ここに書いてください」
とお願いした。
女性は、
「大門一番町」
と書いた。
あのね、ここは七番町。
一番町は、あっちです。
この道を、まっすぐ行くんです。
えんぱーくに出ますから、
そこらへんでもう一度誰かに聞いてください
件(くだん)の女性、私の回答で満足したらしく、
えんぱーくの方向に向かって歩いていった。
筆談も、こうして困っている人の役に立った。
ということで、なんとなく嬉しかった。
それにしても、塩尻の大門の、「○番町」とい標記は、
全く規則性がなくて、
実に分かりにくい。 3/8
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ 養命酒
♪ 朝に養命酒一杯
晩に養命酒一杯
付属の容器で朝夕に飲んで、1か月持ちます。
1700円。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.3.9 (WED)
2016年02月21日
「推測変換候補」(難聴者の脳内作業)
「推測変換候補」
i-PADにも、少し慣れては来ているが、まだまだ、
その機能の百分の一も使っていないと思う。
パソコンとの違いは、入力方法。
下部に表示されるキーボードに入力すると表示部に変換したい文字がズラ~と並び、
その中から選んでいく。
段々と的(まと)が絞られていって、目的のフレーズが確定する。
こう書くと、なんだか面倒そうだが、実際には瞬時に確定する。
こんなことは、ケータイを使っていた者にとってはあたりまえのことだろうが、
私は、ケータイを飛び越えて、一気にタブレットに進んだので、この
「推測変換候補」
という方式が、新鮮である。
これは、難聴者が手書き要約筆記を利用しているときの頭の働きに似ている。
難聴者の頭の中に
「推測変換候補文字表示」
というような機能があると思っていただければよい。
難聴者は、紙に書かれていく文字を見ながら、次を予測しているのである。
要約筆記者が書き終えたとき、利用者も読み終えている、というのが、理想である。
筆記者が書き終えてから、改めて読み直す、というようなことでは、
会議などの切迫した現場では、遅れてしまいます。
それは、筆談の場合も同じである。
黒地の電子ボードでは、筆記者が書いている文字が読みづらい。
このことについて、長野難聴の協会ブログで、
要約筆記者からのコメントをいただいておりますので、引用いたします。
要約筆記サークルの仲間が、電化製品のような、該当のボードを持っていて、(やや高額ですが)ペンの消耗や紙を何枚も用意しなくてすむかな…と思っていましたが、
このように、はっきり白紙に黒文字が良い!とおっしゃっていただき、やはり、利用者の声が一番だと思いました。
黒い電子ボードに、光る文字は、書いていても違和感がありましたし。
ご意見ありがとうございました。
Posted by よね at 2016年02月17日
関連記事(当ブログ1/15)→http://rokumangoku.naganoblog.jp/e1851746.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.2.21 (SUN)
追記 2017.8.20
難聴者が手書き要約筆記を利用しているときの(難聴者の脳内活動を
分析してみました。
パソコン要約筆記で、IP-Talkで、モニターを見ている場合には異なります。
モニター部には、要約筆記者によって正しく変換された文章が出てくるので、
利用者は推測する必要(余地)がない。
文章が表示されるのを、ひたすら待つ以外にない。
パソコンよりも手書きの方が「速い」と感じるのは、そのような意味である。
ところで、私は、パソコン要約筆記のノートテイク利用の場合には、
画面の下方に表示される入力部を見ていることが多い。
つまり、正しく変換される前の文章を見ている。
大概の場合、要約筆記者が正しく変換するのを待たず、わかってしまう。
ただし、このことは、すべての難聴者(利用者)に当てはまることではない、
ということも、また、承知しております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016年01月15日
市販の筆談ボード
黒地の「筆談ボード」はダメです
--- 私は常日頃から、サインペンと用紙は携帯している。
筆談に応じていただくためである。 ーーー
<さて、昨日の記事の続きです>
ドコモショップで、対応を手話から筆談に切り替えていただいた。
、
普通の(つまり手話のできない)店員さんが、喜び勇んで、
というわけではないが、かなり上機嫌で、
市販の筆談ボードを抱えてきた。
店員は、私が机上に出しておいた用紙には目もくれないで、
いきなり、筆談ボードに説明を書きはじめた。
いや、その速度の、
速いこと、速いこと!
要約筆記者でも、あんなには速く書かないだろうというような速さ。
さて、せっかく速く書いてくれて、字もきれいなんだけど、
黒地のボードなので、
書いている最中には、こちらからは全然読めない。
2~3行を書いては、そのボードをこちら向きにしてくれるのだが、
室内照明が反射して、実に読みにくい。
ボードの角度を調節したりして、大変苦労した。
これは多分、会社の方針で、
「難聴者にはこの筆談ボードで対応せよ」
というルールがあるのだろう。
会社とすれば、
なにか、障害者フレンドリーな、
とても親切な、
よいことをやっているように、錯覚しているに違いない。
最近、要約筆記者の中にも、こういうものを持っていらっしゃる方がいる。
ハッキリ申し上げて、市販の筆談ボードはダメである。
遊び感覚で使ったりするには、どうということはないが、
商談とか、大事な場面では、この機種はダメである。
実は、私も以前に、姪から、この機種をプレゼントされた。
「おじちゃんのために」
と、せっかく買ってきてくれたものに対して、
ダメ! 使えない!
とは、言いにくい。
「よく気が付くね、ありがとう」
と言う以外にないのである。
ちなみに、私はこれを数学の計算用紙代わりに使っている。
用途を変えれば、これはこれで、なかなか重宝だ。
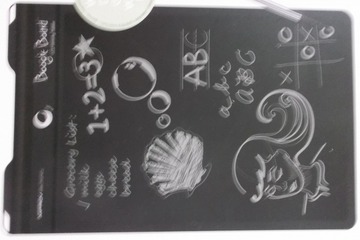
、(商品のイメージ写真)
玩具みたいな商品を
「筆談ボード」
などと称して売りつける偽善のようなことは、
即刻、
止めてもらいたい。
筆談は白い用紙または白地のボードに黒い字で!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
、2016.1.15 (FRI)
--- 私は常日頃から、サインペンと用紙は携帯している。
筆談に応じていただくためである。 ーーー
<さて、昨日の記事の続きです>
ドコモショップで、対応を手話から筆談に切り替えていただいた。
、
普通の(つまり手話のできない)店員さんが、喜び勇んで、
というわけではないが、かなり上機嫌で、
市販の筆談ボードを抱えてきた。
店員は、私が机上に出しておいた用紙には目もくれないで、
いきなり、筆談ボードに説明を書きはじめた。
いや、その速度の、
速いこと、速いこと!
要約筆記者でも、あんなには速く書かないだろうというような速さ。
さて、せっかく速く書いてくれて、字もきれいなんだけど、
黒地のボードなので、
書いている最中には、こちらからは全然読めない。
2~3行を書いては、そのボードをこちら向きにしてくれるのだが、
室内照明が反射して、実に読みにくい。
ボードの角度を調節したりして、大変苦労した。
これは多分、会社の方針で、
「難聴者にはこの筆談ボードで対応せよ」
というルールがあるのだろう。
会社とすれば、
なにか、障害者フレンドリーな、
とても親切な、
よいことをやっているように、錯覚しているに違いない。
最近、要約筆記者の中にも、こういうものを持っていらっしゃる方がいる。
ハッキリ申し上げて、市販の筆談ボードはダメである。
遊び感覚で使ったりするには、どうということはないが、
商談とか、大事な場面では、この機種はダメである。
実は、私も以前に、姪から、この機種をプレゼントされた。
「おじちゃんのために」
と、せっかく買ってきてくれたものに対して、
ダメ! 使えない!
とは、言いにくい。
「よく気が付くね、ありがとう」
と言う以外にないのである。
ちなみに、私はこれを数学の計算用紙代わりに使っている。
用途を変えれば、これはこれで、なかなか重宝だ。
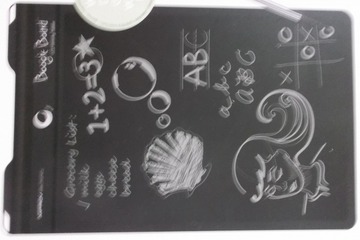
、(商品のイメージ写真)
玩具みたいな商品を
「筆談ボード」
などと称して売りつける偽善のようなことは、
即刻、
止めてもらいたい。
筆談は白い用紙または白地のボードに黒い字で!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
、2016.1.15 (FRI)




